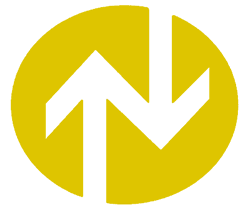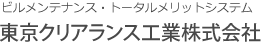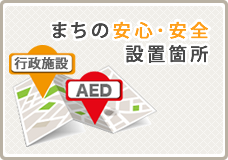エレベーターでの事故にご注意ください
最近、エレベーターによる死亡事故が発生しています。 エレベーターは日常生活に欠くことができないものですが、多くの危険が潜んでいます。ご注意ください。
よくある事故

- 扉や隙間に体が挟まれた
- 中に閉じ込められた
- 正常な位置で止まらなかったり、急停止した
- 戸が開いたまま上昇した
事故を防ぐために
- 大きな事故の前には、かごの停止位置がずれて段差ができる、異音がするなどの異常がみられる場合があります。いつもと違う状況を感じたら、必ずエレベーターの所有者・管理者に伝えてください。
- かごの停止位置がずれたために段差ができてつまづいたり、もし中にかごがなかった場合には転落して大きな事故につながる恐れもあります。かごの状態を確認してから利用してください。
- 慌てて乗り降りすると、扉に挟まれたり、つまづいて転倒したりします。危険ですので、慌てて乗り降りしないようにしましょう。
- エレベーター内に閉じ込められてしまったときには、インターホンで外部と連絡を取り、助けを待ちましょう。インターホンの連絡先はエレベーターによって異なります。日頃使用するエレベーターではどこにつながるのか確認しておくと安心です。
異音や振動はリフト・エレベーターの悲鳴、故障の初期症状に要注意
「最近、エレベーターから変な音がする・・・」というご相談をよくお受けします。
これは、リフト・エレベーターが発する危険信号です。
「なぜ異音が発生するのか?」主な原因としては、
“ガイドレールの油切れ” ”巻上機のブレーキ制御不良” が挙げられます。
異音の原因
ガイドレールの油切れによる異音

異音が発生する原因の一つとしてガイドレールの油切れが挙げられます。
ガイドレールとはエレベーターを導くレールです。カゴはガイドレールに沿って走行します。
電車のレールをイメージして頂ければ分り易いと思います。
通常、カゴとガイドレールの滑りを良くするために、ガイドレールには潤滑油が塗られています。
潤滑油が切れると摩擦により、異音が発生したり、振動が発生します。
ガイドレールの油切れを知らせる異音を放置していると
摩擦がさらに大きくなり、レールとガイドシューと呼ばれる部品が引っかかり、かごの動きも悪くなっていきます。
レールが傷ついたり、ガイドシューも破損します。
業務に支障がでる動きになったり、動かなくなったりした後に修理を依頼すると費用が高額になってしまいます。
巻上機のブレーキ制御不良による異音
異音の原因として、カゴを動かしている巻上機の不具合も考えられます。
リフト・エレベーターの昇降速度は巻上機の減速機によって制御されています。
この減速機の歯車と歯車に隙間ができると震えが発生して、異音が鳴ります。
自転車のブレーキ時にキーキーと音が鳴る現象と似ています。
異音が鳴り続けている状態で使い続けていると、巻上機のブレーキが滑ったり、噛み合い、
ディスクブレーキが潰れてしまいます。
こちらもガイドレールの修理費用と同じく、様々な部品が破損した状態で修理をすると高額になります。
場合によっては修理不可となり、巻上機を交換しなければなりません。
リフト・エレベーターの異音や振動は専門の人でなくても分かる、目に見える不具合です。
この小さい不具合を発見した後、すぐに対応するか、しないかでその後の修理費用に大きな差ができます。
また、目に見える部分だけでなく、目に見えない部分も調べるには、
日々、リフト・エレベーターの点検をしている専門スタッフに任せるのが一番です。
修理費用を抑えるだけでなく、安全を確保するためにも定期的な点検をおすすめします。
エスカレーターは片側をあけない
最近のエスカレーターは片側をあけて、そこを歩いて上り下りするのが一般的になっているが、そもそも、エスカレーターは歩くことを前提にはしていない。
- エスカレーターの安全基準は、ステップ上に立ち止まって利用することを前提 にしています。
- 片側をあけると重量(荷重)バランスが崩れ、不具合を誘発することがあります。
- 歩いたり走ったりしたときに起きる振動で安全装置が働き、緊急停止すること
があります。
(一般社団法人 日本エレベーター協会)
昇降機のメンテナンス・保守点検に関する法律・法令
エレベーターの定期検査・性能検査に関する法令
エレベーターのメンテナンス・定期点検に関しては、建築基準法または労働安全衛生法によって定められています。 一般的にエレベーターのカゴ内側、操作盤上方部に検査済証と呼ばれる書類が貼られています。 この書類の種類によって適用される法律が変わります。
建築基準法/エレベーターの定期検査
建築基準法により定められた検査で、車にも車検があるように、エレベーターにも建築基準法第12条により「定期検査」を行い、その検査結果を特定行政庁に報告することが義務付けられています。これは「エレベーターの安全確保にとって重要な安全装置の試験や、機器の劣化を総合的な面で判定を行う検査」となります。
定期検査の義務について
- 安全上エレベーターの所有者は、年1回定期検査を受けるよう義務づけられています(第12条2項)。
- 定期検査は、建築大臣認定の昇降機検査資格者が行い、その結果を特定行政庁に報告することになっています。
※報告を受けた行政庁は、安全上問題ありと判断した場合は、所有者に是正を勧告、また、重大な不備がある場合は、使用禁止命令を出します。 検査に合格すると、(財)日本昇降機安全センターより「定期検査報告済証」が発行され、かご内に提示されることになります。
労働安全衛生法/エレベーターの性能検査
労働安全衛生法に規定する「特定機械等」のエレベーター検査を性能検査といい、建築基準法第12条第3項に規定する昇降機等の検査を定期検査といいます。
性能検査の義務について
- 「年1回の性能検査」と「月1回の自主検査(点検)」を行わなければならない。
- 年一回の性能検査については、労働基準監督署長または厚生労働大臣の指定する機関(「ボイラー・クレーン協会」「日本クレーン協会」)によって受けなければなりません。また、厚生労働大臣の登録を受けた者(「登録性能検査機関」といいます。)がおこないます(労働安全衛生法第41条第2項)。
労働安全衛生法に適合したエレベーターに関して
労働安全衛生法に規定するエレベーターとは、積載荷重が1トン以上のエレベーター(労働安全衛生法では、「特定機械等」といいます。)をいいます。ただし、このエレベーターは、労働基準法別表第1に規定する事業所に設置されたものを対象とします。